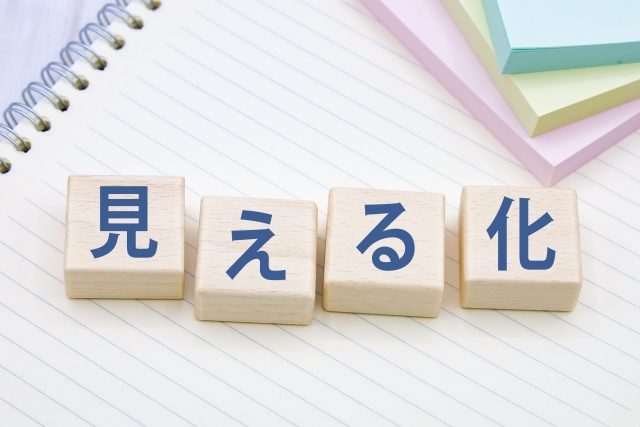こんにちは。Kaziプロジェクトの二戸です。
相変わらず暑い日が続いていますね。熱中症にならないよう、こまめな水分補給を心がけている今日このごろです。
さて、今回は「見える化」というキーワードを起点として、家事の「見える化」について、改めて考えてみたいと思います。
最近はテレビや書籍などでも「見える化」や「言語化」という言葉を多く見聞きするようになりました。人それぞれ解釈はあると思いますが、言葉のとおり、今まで見えていなかった物事を見える化してみよう、というわけですね。
ここで一旦立ち止まり、「見える化」することによるメリット・デメリットはなんなのか、ということを考えてみたいと思います。
1:見える化・言語化することによるメリットとは?
まずはメリットから考えてみましょう。自分の中にあるモヤモヤした感情を「言語化」することによって、自分自身の理解が深まったり、他者に対して適切にメッセージを伝えられるようになります。
誰にとってもそうだと思いますが、捉えきれないモヤモヤしたもの、曖昧なもの、不確定なものはあまり心地よいものではありませんよね。
どこか煮えきれない態度をとっている人に対して、今後どうするのかハッキリ示してほしい!と感じたり、自分の予定を早く決めたいのに、様々な都合で決めることができなくてモヤモヤしたり。
あるいは、有名な芸能人の名前が喉の奥まで出かかっているのに、思い出せない・・・!という状態って、非常にもどかしく感じるものです。
たとえばそこで、曖昧な態度をとっている人の理由が「言語化」されるだけで、モヤモヤが晴れたりするし、もちろん、今後の予定が「見える化」されればスッキリして、気兼ねなく組み立てることができるようになります。
「見える化」することによるメリットは様々あります。中でも大きなポイントは、他者との認識が揃うことにより、コミュニケーションが円滑になったり、問題への対処がしやすいという部分ですね。
あらゆる問題を対処するには、問題自体が「見えていること」が前提であるし、問題を「言語化」し、他者と共有できていることが大前提だからです。
2:見える化・言語化することによるデメリットは?
では次にデメリットを考えてみましょう。まず思い浮かぶのは、「プレッシャーになる」ということです。
たとえば、今の自分の現状を「見える化」してみたら、問題が山積していることを再認識できたとします。それ自体は悪いことではありませんが、やらなければならないことが多すぎて、プレッシャーを感じてしまい、かえって身動きがとれなくなる、なんてことが起きてしまいます。
つまり、今まで「見えていなかった物事」というのは、自分の脳内には存在していなかったわけですが、「見える化」されたことによって、急に脳内の容量が圧迫され、苦しくなってしまうというイメージですね。
だからといって、現実から目を逸らし続けるのも問題があります。どこかのタイミングで対処しなければならない問題は、仮に自分で見える化せずとも、自ずとあらゆるカタチで「目の前に問題として現れる」わけです。
もっと身近な例で考えてみます。たとえば食事のカロリーをすべて「見える化する」というのは、体重をコントロールするうえでは大切かもしれませんが、「美味しものを美味しく食べる」という、本来の食事の楽しみからすこし遠ざかってしまうようにも思えます。
ただ、かといって、好きなものを好きなだけ食べていたら、それはそれで後々、健康になんらかの問題が生じるかもしれません。
見える化することによって対処しなければならない問題と対峙することになり、プレッシャーを感じてしまうこともある。また、見える化することにより、見えていなかったときのほうが楽しく過ごせていたのが、どこか無味乾燥な過ごし方になってしまうかもしれません。
3:家事の見える化はどうなの?
ここで「家事の見える化」について考えてみます。一昔前から「名もなき家事」という言葉を見聞きするようになりました。
「名もなき家事」とは、言ってしまえば「言語化されていない家事」ということですね。言語化されていない、見える化されていないということはつまり、他者と共有されておらず、対処もできないということになります。
「名もなき家事」という言葉がすごいのは、今まで議題に上がってこなかった家事を、「名もなき家事」という言葉で「言語化」したという部分だと思います。
そのような言語化がなされたことにより、細かな家事までもが「見える化」され、代表的な家事(掃除、洗濯、料理…)の他にも、多くの家事が行われている実態が明らかになってきました。
そういった「見える化」の波にのったかどうかはわかりませんが、今はあらゆる自治体で家事分担シートだったり、チェックシートなるものが作成・配布されています。
つまり、名もなき家事も含め、膨大な量の家事が存在することが「可視化」されたわけです。が、しかし、多くの家事を目の前にプレッシャーを感じたり、かえってやる気を削がれてしまうこともあります。
だったら最初から「見える化」なんてしなければよかった?というわけでもありません。
「見える化」することで対処可能になることは確かです。当団体で販売している「家事見える化シート」にも言えることですが、夫婦間での家事の偏りを解消したり、今後の家事分担を考え直すきっかけになるという点では、大きなメリットと言えるでしょう。
ただ、「見える化しすぎ」によって、かえってやる気を削がれたり、あるいは、夫婦喧嘩の種になってしまう可能性すらあります。
まとめると、問題を「見える化」し、対処するのは大切。ただし、あまりにも「見える化しすぎ(細分化)」によって、問題を抱えきれないほどに大きく捉えてしまい、余計なプレッシャーとしてのしかかってくるというデメリットもあるということです。
4:家事の見える化との付き合い方
安易な結論にはなってしまいますが、ようはバランスが大切ということになります。問題を問題として捉えるには、最初は「見える化」が不可欠であり、非常に重要な工程であることには変わりありません。
しかし、見える化する工程で、本来は気にする必要のない部分まで「可視化」されてしまい、かえって問題に取り組む気力が失せてしまうこともあるわけです。
ここで重要なのは、問題として捉えるかどうかのラインを決めるということ。
見える化された問題をすべて対処すべき問題として捉えてしまうと、辛くなってしまいます。なので、見える化された中から、べつに対処しなくてもいい物事は気にせずに放っておくことにする。
そのような付き合い方をすることによって、見える化された家事、あるいは、見える化されすぎた家事と、適切な距離感を保つことができると思います。
手前味噌ではありますが、当団体で販売している「家事見える化シート」は、膨大な量の名もなき家事も考慮したうえで、あえてプレッシャーになりすぎない程度に家事・育児の項目を絞って作成しています。そのような絞られた項目を改めて夫婦間で確認しあい、家事分担を考え直すきっかけになればいいなと思っています。
おわりに
今回は「見える化」について考えてみました。一見よさそうな風潮に思えても、度が過ぎるとデメリットが生じるというのは、どんな物事にも共通して言えそうです。
「見える化」や「言語化」という便利な方法と適切な距離を保ちつつ、快適な暮らしを過ごすきっかけになれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。