アクション名
男性育休推進プロジェクト
株式会社 関・空間設計
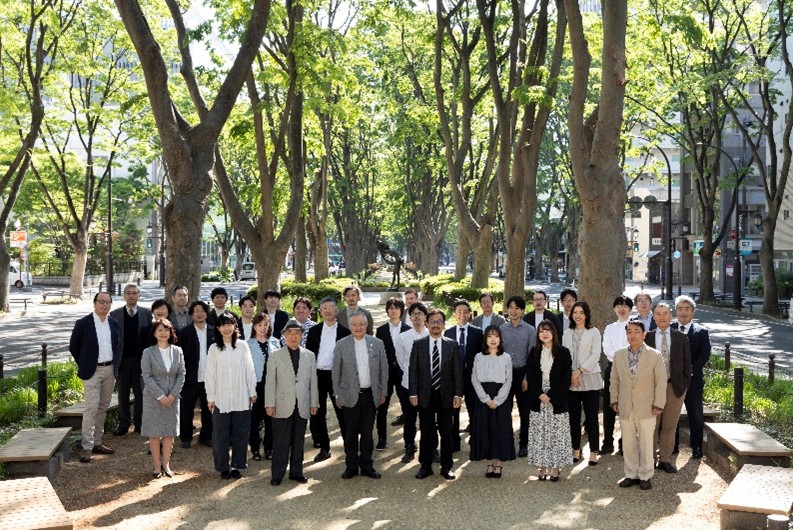
男性従業員
名 前:佐々木 大
年 齢:31歳
入社年数:8年目
部 署:設計監理部
家族構成:妻、長男(5歳)、次男(3歳)、三男(1歳)

男性育休を取得しようと思ったきっかけ
3人の子どもの誕生時、それぞれ育休を取得しています。
長男のときは「育休がどんなものかを少しでも体験してみよう」という思いから、短期間だけ取得し、次男のときは、前回が短すぎたことや在宅中も仕事をしてしまった反省から「家族のためにもう少し長く取りたい」と考えるようになりました。
三男のときは里帰り出産をせず、上の子2人を育てながらの生活になるため、「長めに育休を取らないとやっていけない」と感じたことがきっかけになりました。
取得の目的
産後の妻の体調回復や新生児のケアに加えて、上の子たちをサポートすることを目的にしました。特に三男のときは、家族みんなが健康で安心して暮らせるようにするための大切な期間になりました。
取得方法と期間
まず上司に相談し、その後会社に申請して関係者と業務調整を行いました。
期間は、長男のときが4日間、次男のときが1週間と3日間、三男のときが2か月半(その後半月延長)でした。
育休中の過ごし方
長男・次男が手足口病にかかり、長期間新生児との隔離が必要だったため、実家(長男・次男)と自宅(妻・三男)を往復する生活でした。
手足口病から回復し、やっと家族みんなで過ごせるようになってからは保育園の送迎や食事の支度、お風呂などの育児はもちろん、保育園帰りに公園に寄ったり、買い物をしたりするのが日課となり、忙しいながら楽しい日々を過ごすことができました。
取得して良かったこと、気づいたこと、感想など(仕事、家庭)
出産後の妻の体が一番辛いときに支えられ、夫婦で子育てする喜びを感じることができました。
完全に仕事をしないことは難しかったですが、少し仕事ができる環境があったことで心穏やかに過ごすことができ、復帰もスムーズでした。長期間家に父親がいることで、上の子どもたちが寂しい思いをせずに済んだことも良かった点です。
取得に向けて・育休中・復帰後それぞれの場面での不安や課題と工夫、成果
男性の長期間の育児休暇は会社として初めてだったこともあり、多少の不安はありましたが、上司と相談を重ね、まずは2か月取得してみることで会社も納得してくれました。
育休中も上司と近況報告を実施したことで、柔軟に半月ほど育休期間を延長することができました。
仕事を完全に離れない体制とすることで復帰後の業務もスムーズに行えました。
育休取得をきっかけに「働き方」と「家事育児分担」に変化はあったか
育休をきっかけに家事・育児に、より積極的に参加するようになりました。
夫婦の役割分担も見直し、「二人で協力して家庭を支える」という意識が強まりました。
男性の育休取得率や質を上げるにはどうしたら良いか
まずは夫婦でしっかり話し合い、早めに会社と相談することが重要だと感じています。
会社の理解や、育休中も適切にコミュニケーションを取り続ける体制があれば、安心して取得できると考えています。
また、職場に前例を作ることも取得率や質の向上につながるため、短期間でもまずは取得してみることが大切だと感じています。
育休取得を検討している男性へのメッセージ(宮城県内の中小企業)
最初は後ろめたさを感じ短い育休にしてしまいましたが、3回目にしてまとまった期間を取った結果、不安に感じていたことは特別起きず、家族と過ごす幸せな時間を得ることができました。
迷っている方には、ぜひ思い切って取得してみてほしいです。
会社
取得に向けて・育休中・復帰後それぞれの場面での不安や課題、それらに対して見直したことや工夫したこと、その変化(成果)
私たちは、育児休業を取得する社員と面談し、置かれた状況や不安を丁寧に聞き取ること、そして「どのように育児休業を過ごしたいか」「制度をどう活かすか」を一緒に考えることに力を入れてきました。
「長期でしっかり休みたい」「育休中も一部業務に関わりたい」「収入面が不安」など、希望や悩みは人それぞれです。
本当は長期取得を望んでいながら、周囲に遠慮して短く設定しようとするケースもありました。
そこで、育児休業は権利であることを伝え、本人やご家族が納得できる期間を確保できるようサポートしています。
以前、総務と取得者で面談を行っていた際、上司との間で認識のずれが生じたことがありました。
たとえば、総務としては「育児に専念する必要がある」と判断していた社員に対し、上司は「保育園に預けている時間を使えば業務も可能では」と考えていたケースです。
そこで総務と上司で話し合い、「保育園の時間は母親が休息するためにも必要であること」「業務をすることで家庭内で頼りづらくなる恐れがあること」などを共有し、最終的には育児に専念する方針で一致しました。
この経験から、早期に取得者・上司・総務の三者で方針や業務分担をすり合わせる重要性を実感しました。
現在は安定期に入った段階で三者面談を行い、育休開始まで計画的に準備できる体制を整えています。
さらに、仙台こども財団さんと連携し「パパ育休取得応援ハンドブック」を作成。支援の流れや取得までのステップを明文化し、初めての取得者や上司でも迷わず準備が進められる仕組みを作りました。
こうした取り組みにより、2か月半の育休取得実績ができ、さらに5か月間の希望を自ら表明する社員も現れるなど、これまでにない前向きな変化が生まれています。
三者面談では、上司が総務以上に取得を勧める姿も見られ、育休取得のハードルは確実に下がってきています。
育休・産後パパ育休等に関する研修の実施、相談体制の整備、自社の育休取得の事例提供、制度と育休取得促進に関する方針の周知について、どのように対応したか
私たちは、育児休業制度の取得促進に向けて、研修の実施、相談体制の整備、制度の周知など、段階的に取り組んできました。
市が主催する「パパ力UP講座」への参加をはじめ、社内でも男性の育児参加に関するワークショップや勉強会を複数回開催しています。
これまでの積み重ねにより、お互いに意見を言いやすく、風通しのよい職場風土が育ってきたと感じていました。
しかし、仙台こども財団さんの協力で行った匿名アンケートでは、「男性育児休業は結婚を見据えていない人にとってはメリットがない」「善意での協力には限界がある」という意見も寄せられました。
こうした思いを持つ人がいる限り、育児休業の取得しづらさは解消できないのではと感じました。
私自身、当社で初めて育児休業を取得した経験があります。
休業中は、業務の負担を周りの人達にかけてしまうことへの申し訳なさを強く感じ、「業務を支えてくれる人に何らかの形で報いられる制度があればいい」と思っていました。
そこで、「取りたい人が、取りたい期間を、安心して取得できる」環境を整えるため、会社独自の手当制度を考案しました。
■サポート手当金制度
育児休業を取得する社員の業務を担った人に、会社から感謝の気持ちを手当として支給する制度。
■一律応援金制度
育児に専念する社員を全員で祝い、応援する風土をつくることを目的に、育児休業を1か月以上取得する社員がいた場合、
全員に小額(3,000円)の手当を支給する制度。


利用した助成金
・仙台市男性育休取得奨励金
・両立支援等助成金(厚生労働省)
男性育休の取得・復帰サポートを通して良かったこと、気づいたこと、感想など
取得者が納得のいく育児休業を取得し、感謝の言葉をもらったときや、お子さんを連れて会社に遊びに来てくれたとき、幸せそうに育児をしている姿を見ると、サポートしてきて本当に良かったと心から嬉しく思います。
会社にとっても、育児休業の取得は本人だけでなくチーム全体に良い影響をもたらします。
休業をきっかけに「業務の棚卸し」や「業務分担の見直し」が行われ、属人化の解消や業務の効率化につながります。
また、復帰後の社員は子育てを通じて「マルチタスク力」や「段取り力」が磨かれ、仕事の成長にも結びついています。
社員が子どもを授かることは、本人だけでなく会社にとっても嬉しい出来事です。
育児休業はネガティブな負担ではなく、会社や社員が成長するチャンスだと考えています。
男性の育休取得率や質を上げるにはどうしたら良いか
制度を整えるだけでなく、「使っても大丈夫」と感じられる風土が欠かせないと思います。
社長にお願いして、育児休業取得推進を後押しするメッセージを社員全員に発信してもらいました。
やはり、トップの言葉は大きな影響力を持ちます。
社長の一言が安心を生み、社内の雰囲気を大きく変えてくれたように思います。
また、取得者への配慮だけでなく、支える側にも報いがあるように、応援金制度や業務分担の調整など、周囲も含めた支援の仕組みを用意することが、制度の定着と質の向上につながると感じています。
育休取得を検討している男性とその会社へのメッセージ(宮城県内の中小企業へ)
男性のみなさんへ
育児休業は、「自分と家族がどんな時間を過ごしたいか」を考えて選べる制度で、すべての働く人に保障された権利です。
育児の時間はあっという間ですが、その時期にどう関わるかは、家族にとっても、そして自分自身にとっても、かけがえのない経験になります。
最初に育休を取るのは勇気がいるかもしれません。
でも、あなたが一歩踏み出すことで、次の人が取りやすくなるはずです。
家庭と仕事の両立ができる職場をつくるためにも、どうか遠慮せず、まずはあなた自身が取得してみてください。
他社のみなさんへ
私たちは、育児休業は「一部の人だけの制度」ではなく、職場の柔軟性や強さを高めるきっかけにもなり得ると感じています。
取得する社員だけでなく、支える社員にとっても、業務の見直しやチームの在り方を考える機会となり、結果的に組織全体の力が底上げされることもあります。
また、育休取得を経験した社員は、会社への信頼や帰属意識が高まるとも言われています。
幸せな育児休業を過ごした社員が、次に希望する仲間を自然に応援してくれる場面もありました。
こうした循環が生まれることが、将来の働き方にも良い影響をもたらすのではないかと思っています。
私たちの取り組みはまだ道半ばですが、少しでも皆さまの職場での参考になればうれしく思います。
家庭(妻)
取得前に準備したこと、話し合ったこと
夫婦で「どの程度の期間が必要か」を話し合い、まずは1ヶ月という目安を立てていました。
その後、会社と相談し2ヶ月の取得が決まりました。
また、産後の家庭内における役割分担も産前に決めようと思い、夫が担当する家事・育児などを話し合いました。
具体的には、買い物・料理・掃除・長男次男の育児(保育園への送迎、お風呂)など多くの家事・育児を夫が担当してくれました。
準備・話し合いをしておけば良かったこと
長男のときは準備不足で、家にいながらも仕事をしてしまいました。
もっと具体的に、役割やスケジュール、仕事との距離感を事前に話し合っておけばよかったと反省しています。
次男が生まれたときは、長男に対する精神的な面でのサポートに関することをもっと話し合っておけばよかったと感じました。
出産入院中は夫の実家で母親がいない状況、産後は妻の実家で父親がいない状況で過ごしました。
父親と母親のどちらかがいない状況に長男はかなり不安な様子をしていたので反省しました。
夫の育休取得に向けて・育休中・復帰後それぞれの場面での不安や課題、それらに対して見直したことや工夫したこと、その変化(成果)
夫が育休取得することを聞いたときは、嬉しかった半面、夫の仕事の心配もしましたが、会社側との話し合いの結果、2か月も取得でき、産後の生活を大きく助けてもらえました。
夫の育児休暇中については、休暇前にお互いの役割分担や協力してほしいことなどを明確にしていたので特に不安はなく過ごせました。
産後で大変な状況の中でも家族全員で過ごす時間が増えてとても良かったです。
復帰後については、子ども3人の育児や家事を1人で行うことへの不安が大きかったです。
育児と家事で手一杯だったので、夫の食事や身の回りのことに関しては夫自身に全てお願いしました。
夫が自身の食事作りに加えて子どものおかずも作り置きしてくれたことで負担が軽減されました。
夫の育休取得で良かったこと、気づいたこと、感想など
家事・育児(特に上の子たち)の全般を協力してもらえたことはとても良かったです。
やはり産後1か月くらいは、体調の面で自分の思うように動けないのでとても助かりました。
最初は、「パパの育休は1か月くらいで大丈夫!」と思っていましたが、自分の体調面や子供たちの状況を考えると結果的に2か月以上も育休を取得してくれたことに感謝しています。
男性の育休取得率や質を上げるにはどうしたら良いか
男性の育休取得率に関しては会社の制度や環境が一番関係してくると思います。
また、育休の質に関しては、産後の生活について夫婦で話し合うことが大切だと思います。
子どもが生まれることで今の生活がどのように変わるのか、何が大変になるのかを考えると夫婦で協力することの重要性が見えてくると思います。
夫の育休取得を検討している女性へのメッセージ
実際に夫の育休取得を経験して、育休前の準備期間が重要になってくると感じました。
夫婦での役割分担をある程度明確にするとお互い協力的でより良い育休生活になると思います。
